こんにちは、蕨東口すがやの三代目(野菜ソムリエ)です!
突然ですがコレ、何の野菜を漢字で表しているかわかりますか!?
【甘藍】
答え
↓
↓
↓
「かんらん」と読みまして、実はキャベツのことなんです。
普段見たり聞いたりする野菜達、実は漢字で表記できるものもたくさんあるんですよね。
先日クイズ番組を見ていましたら、ある野菜の漢字名が出題されていまして、、、
野菜ソムリエの資格を持ちながら、悔しいことに解くことが出来ませんでした ^^;
せっかくなので僕の勉強も兼ねて、色々と調べて野菜の漢字名をクイズ形式にしてみました!
ぜひご家族や友人同士で楽しんでもらえると嬉しいです ^^
合コンなどのちょっとした小ネタにも使えるかもですよ 笑
あなたは難問解けるか!?
野菜の漢字クイズ!
第1問
玉蜀黍
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は、、、

とうもろこし
です。
漢字の説明
とうもろこしは、16世紀頃にポルトガルから日本に伝わってきました。
もともと日本には中国大陸から「もろこし」という植物が入ってきていて、そのもろこしに似ていたから「唐(南蛮を意味する)もろこし」と名付けられたそうです。
しかしこの「もろこし」、当時の漢字表記で「唐黍」とされていて、唐という字を当ててしまうと「唐唐黍」になってしまいました。
そのため、唐の代わりに玉(とうもろこしの粒を表す)という字が使われ「玉唐黍」となり、現在では形を変えて玉蜀黍となったようです。(蜀という字に変わった経緯は謎)
野菜ソムリエから一言

第2問
赤茄子・蕃茄
字は違いますが、どちらも同じ野菜の漢字名です。
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

トマト
です。
漢字の説明
そもそもトマトはナス科の植物なんですね。
江戸時代、西洋人がトマトを栽培していて、それを見た日本人が真っ赤な茄子と表現したとも言われています。
諸説ありますが、トマトにはその色から毒があると思い込まれていて、食物として嫌遠されていたことも。
他にもトマトには、小金瓜(こがねうり)、平茄子(ひらなす)、花茄子(はななす)、唐柿(からがき)、珊瑚樹茄子(さんごじゅなす)、などなど、色んな漢字名があるんですよ。
野菜ソムリエから一言

トマトが赤いのは「アントシアニン」という成分が成長過程で増えるから。
ぶどうが紫なのは「ポリフェノール」、にんじんが黄色に近い赤なのは「カロテノイド」
と、野菜が色鮮やかなのは、含まれている天然色素が原因なんですよ〜
第3問
甜瓜・香瓜
字は違いますが、どちらも同じ野菜の漢字名です。
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

メロン
です。
漢字の説明
もともと日本には「真桑瓜(まくわうり)」といわれるメロンに近い瓜がありまして、メロン=真桑瓜とも表現されたりもします。
甜瓜というのは、この真桑瓜の漢名です。
メロンのスペルはMelonですが、これはギリシア語の「melopepon(林檎のような瓜)」から来ているそうな。
古代の人も、メロンを甘いデザートとして食べていたんですね ^^
野菜ソムリエから一言

メロンの生産量、イメージ的には北海道が日本一って思いませんか?
でも実は、日本で一番メロンの生産量が多いのは、、、茨城県なんです!!
あんまり馴染みが無いかもしれませんが、メロンの漬物も生産地ではポピュラーなんですよ。
第4問
糵
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

もやし
です。
漢字の説明
蘖という字は、穀類などを水に浸して、日光を遮断して発芽させたものの総称を指します。
普段あまり見かけない字ですが、この蘖という字の他にも「萌やし」という字を使うこともあるんですよ!
「萌やし」となると、急にかわいく感じますね 笑
野菜ソムリエから一言

私達が普段食べているもやしは、緑豆・小豆・大豆を発芽させたものです。
大麦からももやしを育てられますが、それらはビールの原材料となるんですよ ^^
第5問
芽花椰菜
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

ブロッコリー
です。
漢字の説明
ブロッコリーを和名で言うとメハナヤサイ。
芽花椰菜でなく、芽花野菜とも書けるそうです。
中国語だと椰菜だけでブロッコリーを意味します。
この他にも「ミドリハナヤサイ」とも言われることもあり、緑花椰菜でもブロッコリーを指す字になります ^^
野菜ソムリエから一言

芽花椰菜、これだけで料理の名前みたいですね〜。
ブロッコリー、実は房のとこよりも軸の所の方が甘みや旨味があり美味しいんですよ!
房だけ取って残りを捨てちゃうなんて、とってももったいない!
外側の硬い部分を切って、内側の部分をぜひ召し上がってみて下さい ^^
第6問
竜髭菜
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

アスパラガス
です。
漢字の説明
アスパラガスの容姿から、この竜髭菜という字が当てられました。
龍のヒゲに例えるなんて、とってもオシャレですよね。
日本語の別名で言うとマツバウドという名前もあるのですが、、、
漢字で書くと、、、「松葉土当帰」と、急にゴツゴツしい名前になってしまいますね ^^;
野菜ソムリエから一言

アスパラにはアスパラギン酸という旨味の元がたっぷりと含まれていますので、茹で汁などはスープに使うと良いですよ ^^
また、細いのや太いのがありますが、繊維の数は一緒。
なので、太いものを選んだ方が、柔らかく食べごたえもあって美味しいです!
第7問
和蘭芹
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

パセリ
です。
漢字の説明
和蘭芹の意味は「オランダのセリ」。
パセリ自体もセリ科の植物ですし、舶来からやってきたパセリは、オランダのセリと名付けられたのでしょう。
野菜ソムリエから一言

パセリ、苦手な人も多いですよね、、、
僕も香草があまり得意じゃないので、パセリもちょっと苦手です ^^;
しかし、乾燥させたパセリは香りも落ち着き、料理の色付けにとっても便利!
やっぱり料理に緑色が入ると、それだけで色合いが鮮やかになりますよね ^^
第8問
陸蓮根
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

オクラ
です。
漢字の説明
オクラ、実はそれ自体が英語名(okra)!
元々オクラは日本全国に普及する前、沖縄・鹿児島エリアで早くから食用とされていて、その地方での呼び方をネリと言っていたそうです。
ネリというのは、オクラのネバネバをさらに練って、和紙などの材料にしていたことから由来しています。
具体的にはアメリカネリと言い、その他に陸蓮根(おかれんこん)という異名も付けられていました。
野菜ソムリエから一言

オクラって、確かに小さい頃には馴染みの薄かった野菜だった気がします。
昭和50年代以降、栽培方法も確立されて、全国的に普及されたようですよ。
第9問
桜桃
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

さくらんぼ
です。
漢字の説明
桜桃と書いて「おうとう」と読みますが、白い花を付けるサクラの木の一種を指します。
この桜桃に付く実のことをサクランボと言いますが、「桜ん坊」と書いてもサクランボです ^^
字だけ見ると春の季語っぽいですが、サクランボの収穫時期は夏なので、サクランボの季語は夏です!
野菜ソムリエから一言

大塚愛さんの名曲で「サクランボ」がありますが、あれは実が対になっている姿が可愛くてタイトルを付けたらしく、、、
作曲者本人はサクランボ自体あまり好きじゃないらしいです 笑
サクランボといえばやはり有名なのは山形産の「佐藤錦」ですが、2013年の初競りでは一箱12万円の値段もついたことがあるそうな、、、
第10問
塘蒿
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

セロリ
です。
漢字の説明
まず、塘(つつみ)と蒿(とう・ヨモギ)と分解出来ます。
塘というのは水たまり、または水を溜めるために作り上げた土手を指す字。
蒿はその名が当てられているように、ヨモギという1年草だったり、高く背の伸びる雑草を指す字です。
なので、水が多い土地に背が高く伸びている姿からこの漢字が当てられたのかもしれませんね。(あくまで憶測ですが ^^;)
セロリは、豊臣秀吉の家臣である加藤清正が、文禄・慶長の役の際に日本に持ち帰ったという説もあります。
そのため、清正人参という名前も、セロリとして当てはまります ^^
野菜ソムリエから一言

セロリも好き嫌いが分かれる野菜ですよね〜
香りが強いものはどうしても好き嫌いがハッキリしちゃいます。
ただ、セロリは香味野菜としてとっても有能な野菜。
トマトソースやクリームソースを作る際、人参・玉ねぎなどと一緒に炒めて香りを出しますと、嫌な香りは消えて、味にさらに深みが増しますよ ^^
第11問
忍辱・大蒜
字は違いますが、どちらも同じ野菜の漢字名です。
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

にんにく
です。
漢字の説明
忍辱という字は、困難を耐え忍ぶという意味の仏教語から由来しているそうです。
禅宗では、強壮作用が煩悩を増幅させると認識されていて、ネギ、ラッキョウ、タマネギ、ニラなどと共に食べることを禁じられていたそうです。
それでも耐え忍ぶというくらいですから、当時の人も本当は食べたかったのでは 笑
また、大蒜というのはオオビルと読みまして、中国での呼び方を表します。
そのため、日本でにんにくを漢字表記する際も大蒜と書くんですね。
野菜ソムリエから一言

にんにく、香りを気にしてしまいますが、とっても美味しいですよね〜
ラーメンにもたっぷりとおろしにんにくを入れたい派です。
にんにくの香りの原因は、アリシンと呼ばれる成分。
すりおろすことでさらに成分が強くなりますので、生ニンニクよりもおろした方が香りが強いんですね。
たちの悪いことに、にんにくを食べると血液と結合として全身に行き渡りますので、口臭予防や水分を多めにとっても消臭にはあまり効果がないのが実際のところ。
にんにく料理を食べる際、牛乳を一緒に飲むと、牛乳のタンパク質がアリシンの吸収を抑えてくれるようです。
といっても、臭うものは臭いますけどね 笑
第12問
糸瓜
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

ヘチマ
です。
漢字の説明
果実から繊維が取れることから、糸瓜という字が当てられました。
ヘチマとなぜ呼ばれたのかは諸説ありますが、「いとうり」が「とうり」と訛り、「と」はいろは歌の「へ」と「ち」の間にあることから「へちまうり→へちま」になったそうな。(これはかなり弱い説らしいのですが。)
ちなみに沖縄ではヘチマのことを「ナーベラー」と言います。
これは、ヘチマをスポンジ代わりに鍋洗いとして使っていたから、この名前になったそうです ^^
野菜ソムリエから一言

ヘチマは関東ではあまり食べませんが、沖縄ではよく食べられる野菜の一つです。
沖縄出身の母が以前作ってくれましたが、ナーベラーチャンプルなんて料理もとっても美味です。
食感は茄子みたいな感じなので、全然クセなく食べられますよ ^^
第13問
蜜柑
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

みかん
です。
漢字の説明
これは読みやすいし、雰囲気的にも伝わりやすそうだったので、簡単だったかもしれませんね!
甘い柑橘ということから「蜜柑」と付けられましたが、昔は「みっかん」と発音していたようです。
日本で食べられている殆どの品種は温州みかんですが、名産地だった中国浙江省の温州から由来しています。
野菜ソムリエから一言

冬にこたつの上にある果物といえば、やっぱりみかんですよね。
みかんを食べる時に薄皮についているスジを取ると思いますが、あのスジの正式名称は「維管束(いかんそく)」と言います。
みかんに水分や栄養分を送るためのものですが、食物繊維が豊富なので出来るだけそのまま食べた方が良いですよ ^^
ちなみにみかんのつぶつぶのことは、「砂瓤(さじょう)」と言います。
第14問
萵苣
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

レタス
です。
漢字の説明
萵苣と書いて「ちしゃ」と読みます。
切ると白い乳汁をが出ることから「乳草」と呼ばれ字が変わったという説や、「小さい草」の呼ばれ方が転じて「ちしゃ」になったという説も。
萵苣にはカキヂシャとタマヂシャの2種類があり、日本では古くから結球(玉状になること)しない、カキヂシャが栽培されていました。
明治以降、結球型のタマヂシャが輸入され、以後レタスと呼ばれ大きく普及していきました。
野菜ソムリエから一言

レタスと言えば食物繊維!というイメージですが、実はレタスに含まれる食物繊維はとっても少ないんです。
その量、100g中1.1gしか摂取できません。
食物繊維を取るなら、オススメなのがゴボウです。
100g中6.1gとレタスの6倍の含有量!
とはいえゴボウを100gも一気に食べるのは難しいですから、レタスのサラダと一緒に、きんぴらごぼうなどを副菜に添えてもらえるとベターです ^^
第15問
菠薐草
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

ほうれんそう
です。
漢字の説明
菠薐草の菠薐は、原産地であるペルシャ(現:イラン)を指しています。
ペルシャの草=菠薐草なのですね ^^
ほうれん草には東洋種と西洋種があり、現在私達が口にしているのは殆ど西洋種。
江戸時代、江戸のブランド野菜であった小松菜が大変人気で、ほうれん草はアクも強いためにあまり人気がなかったようです。
野菜ソムリエから一言

ほうれん草と言えばポパイ!!(もはや古い?)
これは完全にイメージ戦略で、ほうれん草のPRでしかありません 笑
放映当時、アメリカではポパイ効果でほうれん草の需要量が10年間で6倍になったという話があります。
日本でもその波は受け継がれ、現在は人気1番の青菜となっています。
第16問
蕨
[wpex more=”【正解を見る】” less=”正解を隠す”]
正解は

わらび
です 笑
漢字の説明
僕の地元でもある「蕨」。
このブログを読んで下さっている蕨在住の方には超簡単な問題だったはず 笑
蕨(わらび)とはイノモトソウ科の多年生のシダのこと。
山や草原など、日当たりのよい所に生えています。
こぶし状にクルンとしている若葉は茹でたり炊き込みご飯に入れたり食用になります。
根茎は砕くことででんぷんが取れ、これを粉状にしたものがわらび粉となり、わらび粉を使ったお菓子がわらび餅です。
野菜ソムリエから一言

蕨という字、住んでいると当たり前のように読み書き出来るのですが、、、
馴染みのない人には、読めない&書けないのが当たり前!
書き方のコツとしては、、、
くさかんむり書いて、がんだれ(広のチョンが無いやつ)書いて、逆の中だけ書いて、欠を書く! 笑
これであなたも蕨って書けますね ^^
家族で楽しめる【野菜の漢字クイズ】まとめ
いかがでしたでしょうか ^^
普段カタカナ表記で見ている野菜も、実は漢字名があるんですよね。
漢字だけでなく、その成り立ちや由来も知ってみると色々と面白かったりします。
ぜひ、カタカナの野菜を見かけたら、日本名や漢字名があるかどうか探してみてくださいね ^^
野菜ソムリエの資格に興味がある方へ
この記事は、野菜ソムリエとしての知識を活用して書き上げました。
こういった野菜の知識は、野菜ソムリエの講座を通して、楽しく学ぶことが出来ます。
野菜ソムリエに興味がある方は、ぜひこちらの記事もご覧下さい↓
[nlink url=”https://www.sugaya-east.com/blog/junior-vegetable-about/”]

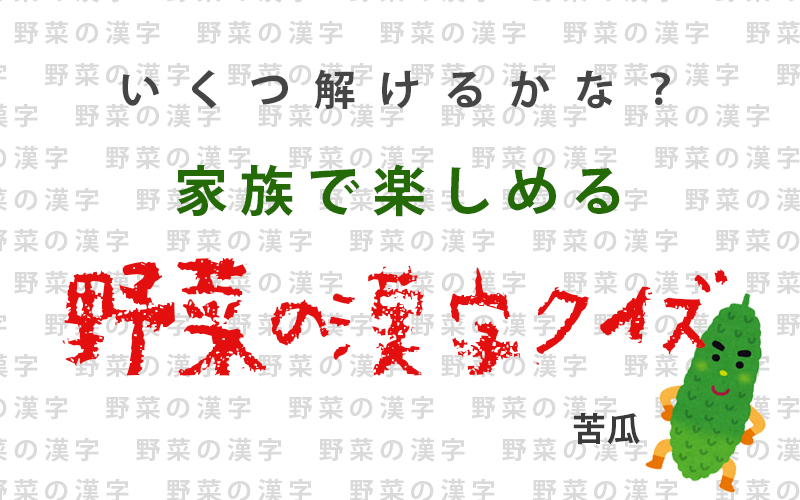




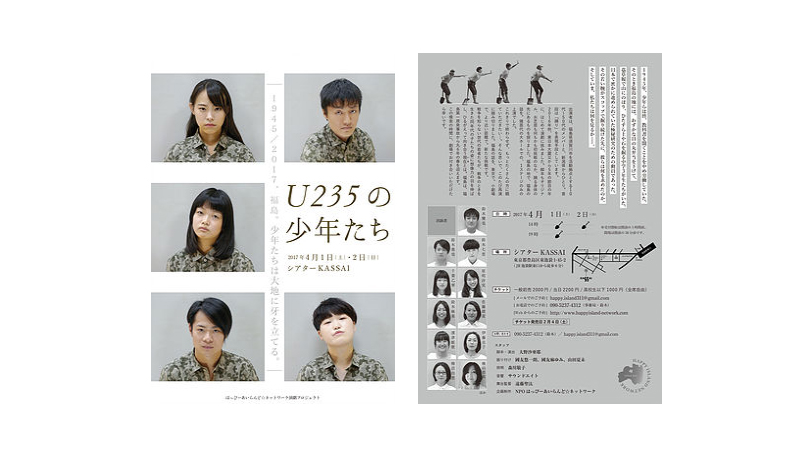
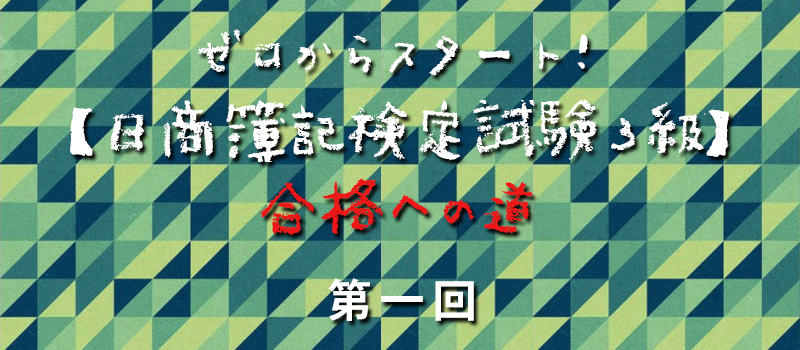
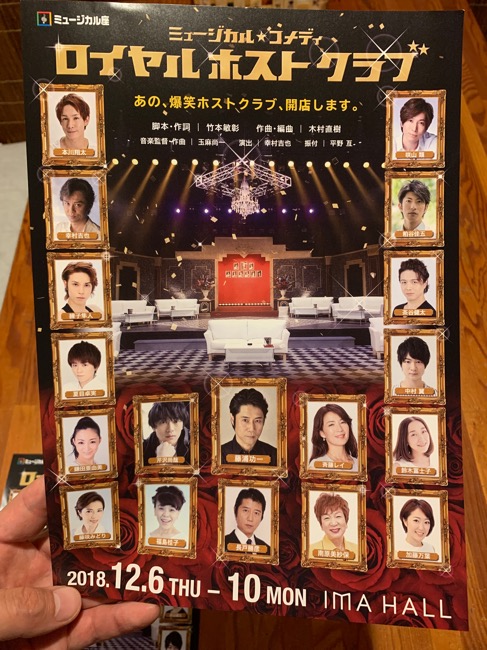

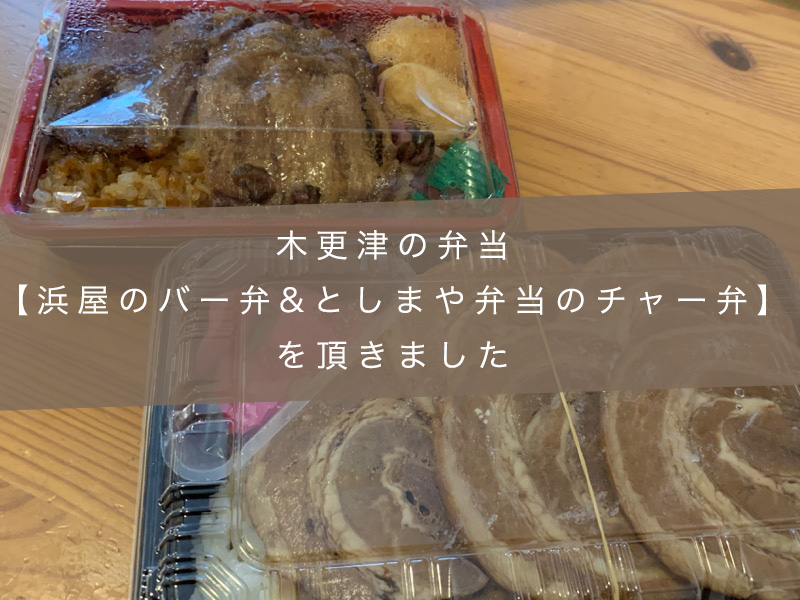


粒粒が並んでいる様子を、玉という字で表すのが当時の人の発想の素晴らしさですよね〜。
それにしても「玉蜀黍」、、、三国志の武将っぽい!