こんにちは、蕨東口すがやの三代目(野菜ソムリエ)です。
今朝、市場へ買い出しに行きましたら、、、
なんとロマネスコが安売りしてたので迷わず即買いでした!
この世にも奇妙な形をした野菜【ロマネスコ】
一眼のマクロカメラで撮ってみたので、ぜひぜひ馴染みのない方は写真を見てその魅力に触れてみてください 。
ロマネスコの概要
日本でのロマネスコという名前は、イタリア語での呼び名である Broccolo Romanesco(ブロッコロ・ロマネスコ、ローマのカリフラワーの意)に由来する。
未成熟の花蕾と花梗を食用にする。アブラナ科の野菜の中では比較的穏やかで微かに甘い芳香を持つ。
花蕾群の配列がフラクタル形状を示す特徴を持つ。
16世紀にローマ近郊で開発されたとされている。
これには異論もあり、ドイツでも同時期から栽培の記録がある。色は黄緑色(クリーム色から緑色の中間色)で、姿はブロッコリーに近く背が高めで葉は展開する。
一方、頂花蕾のみで側枝は発達せずカリフラワーの性質を示す。
味はブロッコリーに近く、食感はカリフラワーに近い。
この様に中間的な性質から、野菜市場、種子市場ともにどちらの品種とするか混乱がある。
さらに緑色のカリフラワー(broccoflower)との混同が、これに輪を掛けている。
現状では分類上はカリフラワーだが、呼び名はブロッコリー(英: Romanesco broccoli)が優勢となっている。
ロマネスコの花蕾は幾何学的な配置となっており、個々の蕾が規則正しい螺旋を描いて円錐を成している。
円錐はさらにそれ自体が螺旋を描いて配列し、これが数段階繰り返されて自己相似の様相を呈する。
また、配列した蕾や円錐の数はフィボナッチ数に一致することも知られている。
その形状からサンゴに見立て「黄緑サンゴ」とも称される。
甘みはそれほどなく、コリコリとした食感をもつ。
【出典:ウィキペディア】
と、難しい概要ですが、要はとっても面白い形をした野菜というのが際だっているのです 笑
文章はともかく、今日はガンガン写真を載せますね。
ロマネスコの写真

埼玉県産のロマネスコです。
どの辺で栽培されているんだろう?

袋から取り出すとこんな感じです。
周りの葉がある程度カットされていますが、本来はもっと外葉に包まれています。

房の一部のアップ。
一つ一つを形成しているものが全体と同じ形をしています。
このことをフィボナッチ数と言いまして、この幾何学模様が非常に美しい!

さらにアップ。
見れば見るほど不思議です。
この渦巻型が何で出来るんでしょう?

もう一度全体像。
まるで花束のようですね。

色もカリフラワーとブロッコリーの中間くらいの淡い緑色。
パステルカラーでとても可愛いですね ^^

茎を下にして立たせてみました ^^
このロマネスコの存在感!
オブジェとしても飾ることができそうです 笑

上から見た図
全体も放射状ですが、一つ一つも放射状に形を形成していますね。

周りの葉と茎を落とし、スリムになりました 笑
この下の部分も、外側を少しカットすればブロッコリーやカリフラワーと同様に美味しく食べられます ^^

ペティナイフで小房を一つ切ってみました。
小房にしてもわかりますが、全体像と同じ形をしています。

全体からパーツへと、グラデーション 笑
同じ形で小さくなっていくのがわかります!

最も小さい房。
頑張ればさらに切ることも出来そうですが、その一つ一つも同様に同じ形。

小房のさらにアップ!
見れば見るほど本当に引き込まれますね。
世にも不思議なロマネスコ、楽しんで頂けましたでしょうか ^^
最近では一般的なスーパーでも目にすることがありますので、ぜひ手にとって見て欲しいと思います ^^
次回は、実際に調理しているところもブログにアップしようと思います♪
追記:実際に調理した記事も書きました↓
■関連記事
【ロマネスコ】の切り方・下ごしらえ・保存方法・食べ方のまとめ
野菜ソムリエの資格に興味がある方へ
この記事は、野菜ソムリエとしての知識を活用して書き上げました。
こういった野菜の知識は、野菜ソムリエの講座を通して、楽しく学ぶことが出来ます。
野菜ソムリエに興味がある方は、ぜひこちらの記事もご覧下さい↓
【野菜ソムリエとはどんな資格?】現役の野菜ソムリエが詳しく解説







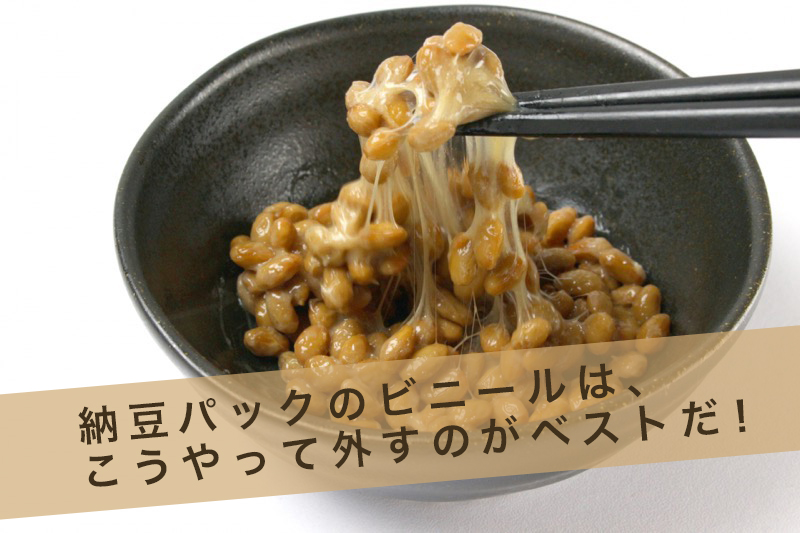

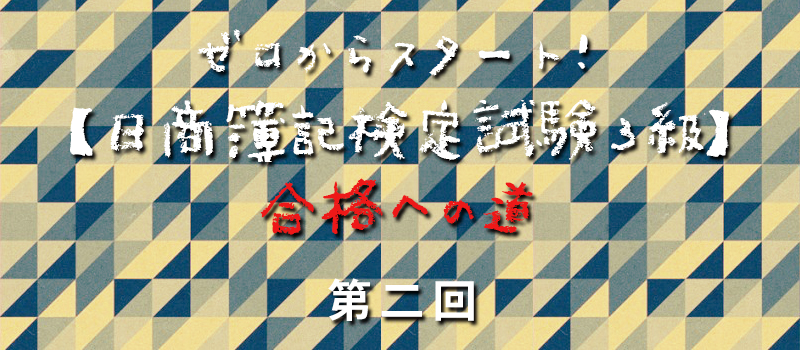
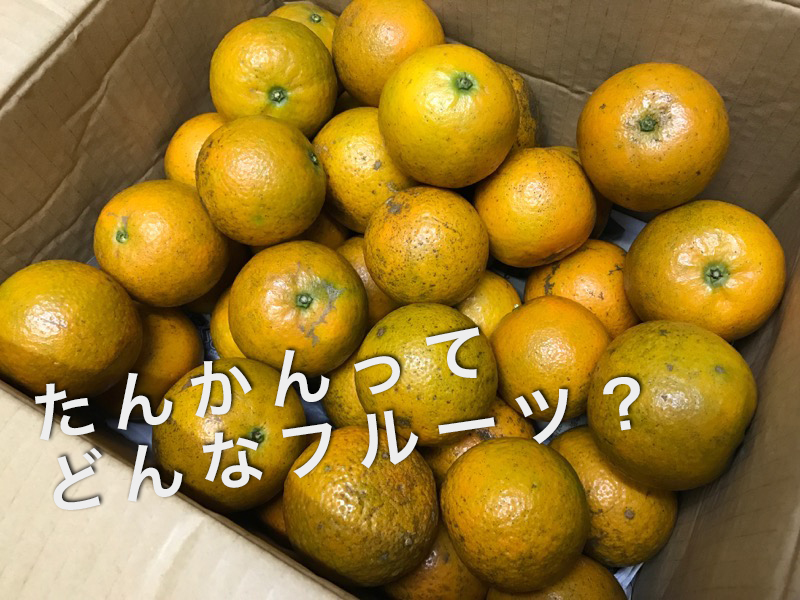
コメントを残す